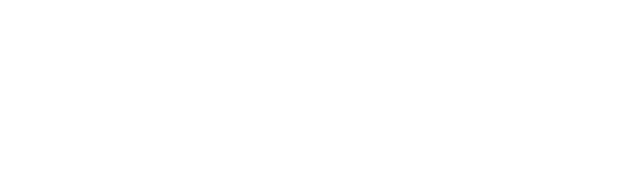#24 推理作家 貫井徳郎さん〈後編〉
“日々の小さな幸せを見つけることが
執筆のモチベーションに”
『愚行録』『乱反射』『微笑む人』等、映像化や漫画化された作品でもおなじみの推理作家・貫井徳郎さん。本格的なミステリーのトリックを軸に、さまざまな分野や手法に挑んだ意欲的な小説を次々と発表されています。去る10月2日には、本学附属図書館ホールにて「執筆は趣味」と題する特別講演会にご出演くださいました。本との出会いや思い出、小説を書き始めたきっかけ(前編)、執筆のアイデアの出し方、モチベーションを保つ秘訣、医療を学ぶ学生たちへのメッセージ(後編)などをお話しいただきました。

貫井徳郎(ぬくい・とくろう)
1968年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒。1993年に第4回鮎川哲也賞の最終候補となった『慟哭』でデビュー。2010年『乱反射』で第63回日本推理作家協会賞長編及び連作短編集部門を、『後悔と真実の色』で第23回山本周五郎賞を受賞。『愚行録』『悪の芽』『邯鄲の島遙かなり』『紙の梟 ハーシュソサエティ』『龍の墓』『ひとつの祖国』など著作多数。最新刊は『不等辺五角形』。
―執筆のアイデアの出し方は?
仕事場の机に向かって根性でひねり出しています。長年続けているとアイデアの出し方も職人技のように身に付いてきているようです。漠然としたイメージのみで書き出すタイプで、連載小説の最終章で急遽ラストを変えることもあります。執筆で大切にしていることは、文章のリズム。特にミステリー作品は、後から遡って伏線を付け加えることも結構あると思うんですが、そういうのはリズムが悪くなるんです。極力、そうならないように、文章が澱まないように意識しています。私の文章は、文体も結構硬くて、難しい表現も使い、改行も少なくて、活字がびっしり。本来は読みづらいはずなのですが、「読みやすい」と言っていただけるのはリズムを大事にしているからではないかと思います。アイデアの着想は「これまでやってないことを探す」でしょうか。誰もやっていないことが理想ですが、毎回それを見つけるのは不可能なので、少なくとも自分がこれまでやっていないことを探しています。テーマでも、形式でもいいんです。例えば、男女が交互に語ることで、同じものを見ていても全く異なる視点であることを描くとか。他の作家の方の作品を読んで「あ、この手があったか」と気づくこともよくあります。
―小説家としてモチベーションを保ち続ける秘訣は?
初心を忘れないこと。気づけば30年以上、執筆していますが、今でも自分の作品が本になるのは嬉しいし、読んでくださる方がいるのは幸せなことだと感謝しています。それから、自分の心の動きの中で小さな幸せを見つけること。本当に些細なことですよ。一日トラブルもなく何も起きず平穏に終わったとか、小説がうまく書けたとかね。私は達成感中毒で、小さなことでもクリアできると嬉しいんです。好きなゲームのクエストがクリアできた、原稿締切を無事に終えた、細々した雑用を片付けたなど、ちょっとした目標達成に喜びを感じています。一日のルーティンでいうと、午前中は運動をして、お昼ご飯を食べたら、お気に入りのドラマを1本見て、ちょっとゲームをやって、それから仕事場に行って執筆。夕方には帰宅して、晩ご飯の後は読書です。私にとっては毎日のドラマとゲームがご褒美で、順番が逆なんですが、自分にご褒美を与えてから仕事に集中しています。自分へのご褒美はまさに小さな幸せですし、スケジュール通りに一日を過ごせることも目標達成できたという幸せなんです。あとは、週に一度、必ず行ったことのないところに散歩に行きます。東京はあちこち行き尽くしたので、行ってないところを探すのも一苦労ですが、見たことのない風景を目にするのは、刺激やインプットになっています。こうした日々の小さな幸せが、執筆へのモチベーションに繋がっています。

―京都府立医科大学で学ぶ学生たちへメッセージをお願いします。
私自身、人生も後半に入ってきて、頭が柔らかいうちにたくさん勉強しておいてよかったなと思います。勉強は人生においてずっと続くものだけれど、若い頃に吸収したことはいつまでも残ります。今、吸収できることはどんどん吸収しておいて、絶対に損することはないはずです。今の勉強は必ず報われます。そして、何かを目指して頑張っていること自体がどれほど幸せかということは、後にならないと気づかないんです。目標があるなら、諦めずに力を尽くして欲しい。それが自分の人生の糧になります。ぜひ頑張ってください。