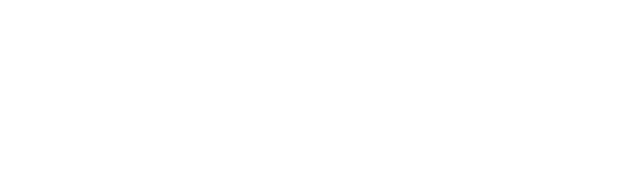#5 特別編② 坂上 雄(さかうえ・ゆう)さん
大学院医学研究科 博士課程2年生 / 循環器内科
“多くの刺激に溢れる 贅沢な学びの時間”

京都府立医科大学では、未来の医学・医療、社会に貢献したいという高い志をもった学生たちが日々勉学や研究に励み、附属病院での実習を積み重ねています。今回は特別編として、循環器内科の臨床業務と遺伝子領域の研究を両立する大学院医学研究科博士課程2年生の坂上雄さんにお話を聞きました。
―これまでのキャリアについてお聞かせください。
平成27年(2015年)本学医学部を卒業後、旧・公立南丹病院(現・京都中部総合医療センター)と京都府立医科大学附属病院とのたすきがけ(1年ごとに交互)で臨床研修を終えました。循環器内科は心筋梗塞や不整脈、急性下肢動脈閉塞など1分1秒を争う緊急性の高い処置が多く「自分にできるのだろうか」という不安もありました。府立医大の先生方の「なんとかなるよ」という言葉に単純な私は背中を押されて専攻を決心することになりました。医師3年目から6年間、京都中部総合医療センターの循環器内科で勤務しました。当科では、卒後6年目で大学院に進学するのが標準的で、私の場合は3年遅くなったわけですが、同じ病院に6年間勤め、お互いの関係性を構築できた患者さんの診療を続けられたことは一つの財産だと思っています。この間、多忙ながら40回の学会発表にも取り組みました。また平成27年(2015年)からこれまで7回、亀岡ハーフマラソンにメディカルランナーとして参加しています。幸いこれまで参加者のメディカル対応はありませんが、これも貴重な経験です。
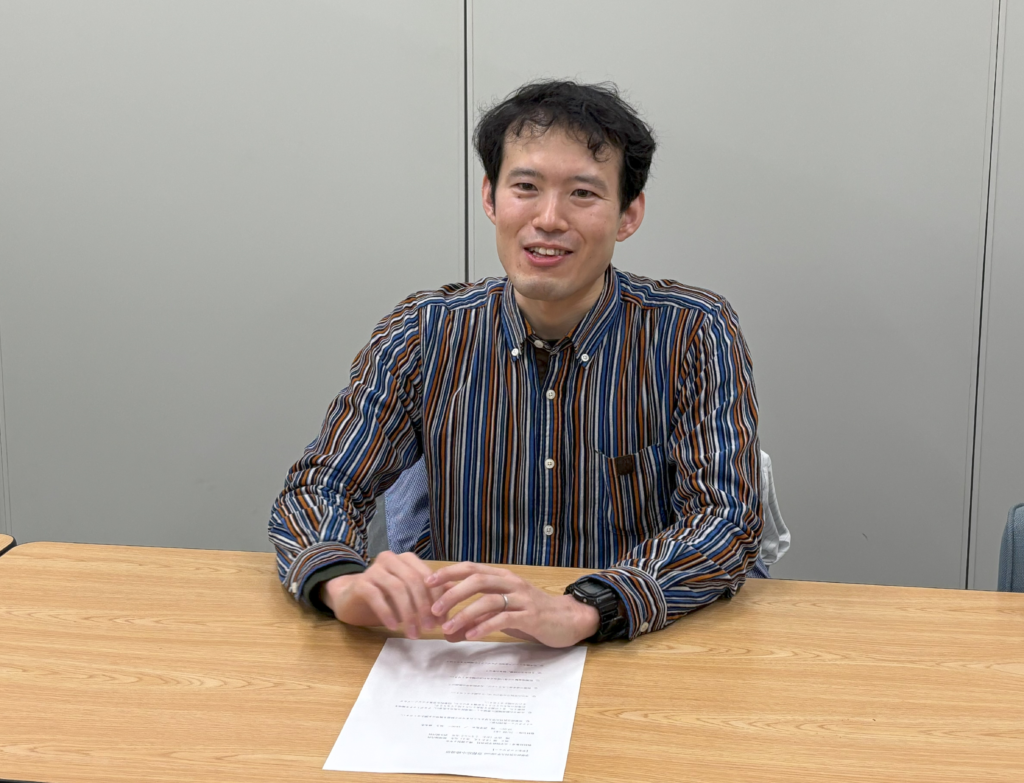
―大学院ではどんな学びを?
6年間の臨床業務で「やりきった」「燃え尽きた」と感じ、全く違うことをやってみたいという気持ちの変化がありました。大学院では、星野温講師のもとで与えられたテーマを研究しています。メインのテーマは「脂肪萎縮症に対する新規治療」、そして星野先生が取り組んでいる遺伝子編集技術の一種「CRISPR-Cas9(クリスパー・キャスナイン)」の研究にも関わっています。これは、全遺伝情報(ゲノム)を、特殊な構造を使って自在に編集できる技術で、2020年には開発者であるドイツとアメリカの女性研究員2人がノーベル化学賞を受賞しました。まだ一般的な治療として臨床応用されていませんが、狙った部分を極めて正確に切断したり、切断したところに別の遺伝情報を組み入れたりすることができるため、効かせたい部分へ確実に安全に到達させるための小型化・効率化を研究しています。最先端であり、これから非常に期待されている領域です。循環器とはまだ関係が乏しい分野ですが、心臓に関連付けて還元できればと考えています。星野先生の志としては、日本最先端を行くに止まらず、世界と闘うことを視野に入れておられます。昨年、研究グループの先輩が、東京大学・自治医科大学との協力で執筆した論文がアメリカの科学誌『Cell』に掲載されました。星野先生の指導は厳しいですが、世界へ挑む覚悟で研究されている人の背中を見られることは、多くの刺激に溢れており、贅沢な学びの時間だと思っています。
―家庭と研究の両立のための工夫は?
臨床業務と大学院での研究、それに加えて家族との家庭生活もあります。妻は小児科の医師です。妻の勤務病院に近い神戸の自宅で妻と子どもは生活しており、私は大学院への通学もありますので京都にも生活拠点を設け、週3回京都、週4回神戸、あるいはその逆という日々です。妻も多忙で、子どもはまだ4歳なので子育ては東京の義母にも協力してもらっています。毎週日曜に飛行機で神戸へ来ていただいて、日曜日と月~木曜日の保育園以外の時間は面倒を見てもらっています。義母も仕事があり木~金曜日は東京に戻られます。その間は私の両親にも助けてもらい、まさに家族一丸のチームワークで子育てをしています。妻、両親、義父母の多大な協力、健やかに成長してくれているわが子にも感謝しながら、研究に取り組んでいます。
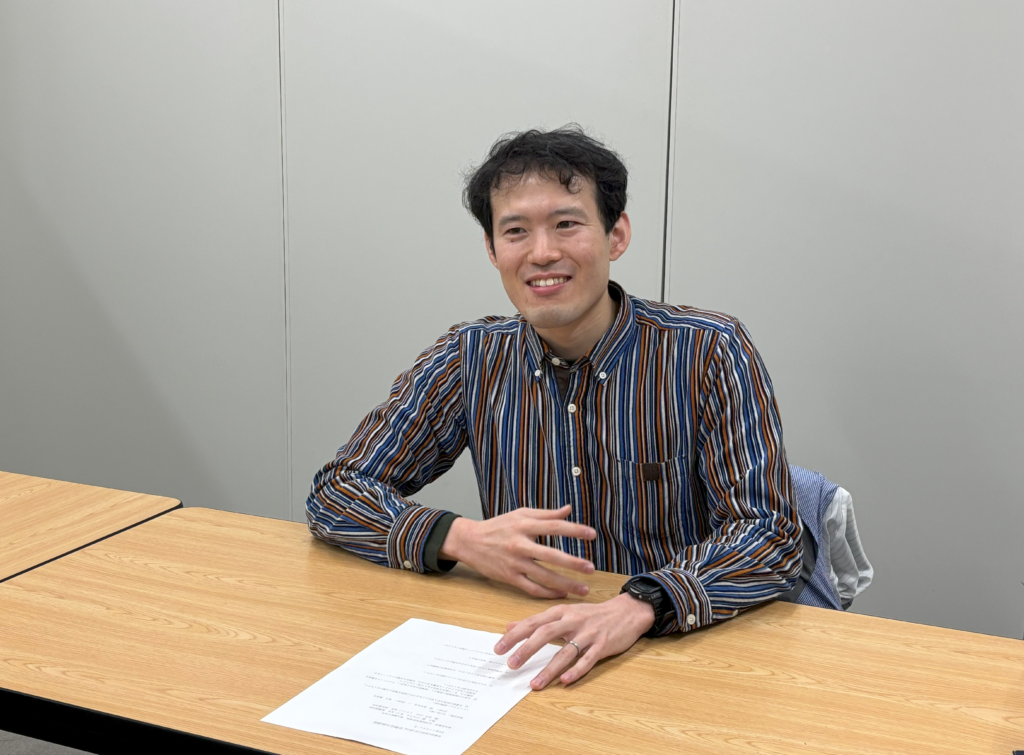
―府立医科大学時代の図書館での思い出は?
大学生の頃は、試験前にはよく来て勉強していて、医師国家試験が近づくにつれ、図書館にいる時間はどんどん長くなっていました。国家試験対策オンライン塾のWEB授業があって、どこでも受講できるんですが、図書館は静かで、気持ちも落ち着いて集中できたんですね。インターネット環境さえ整っていれば、カフェでも自宅でもできますが、気が散ったり誘惑に負けてしまったり。図書館が一番効率よく勉強できました。同じように勉強している学生も多くて席取りが大変でしたが、モチベーションも高まりました。広小路キャンパス活性化プロジェクトの一環で1階にラーニングコモンズができると聞きました。みんなで勉強会やグループ発表などもできますし、学生にとってはきっとプラスに働くと思います。図書館ホールで学会が開催されることもあり、ホールでの発表の後、ラーニングコモンズを使って懇親会や分科会、ポスターセッションなどもできます。交流の場として、今後さらに開かれていくことを期待しています。