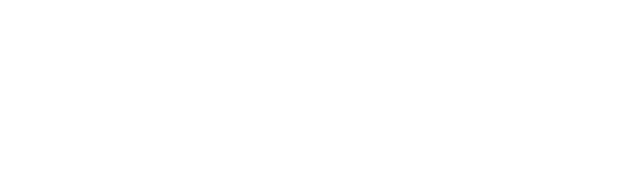#9 図書館ホール+ラーニングコモンズ活用事例 京都クオリアフォーラム「第7回お互いを知ろうの会」〈後編〉
“斬新な芸術や京都の伝統文化を通して 新しい出会いを創出”

令和7年4月、京都府立医科大学附属図書館内にラーニングコモンズ「Koto Square」が完成しました。4月8日にテープカットと内覧会を行い、翌9日はこけら落としとして、京都クオリアフォーラムの「第7回お互いを知ろうの会」を開催。2階の図書館ホールとの併用で活動報告、部会ミーティング、デモ展示など、産学、異業種の方々約100名の参加がありました。京都クオリアフォーラムの運営にも携わる京都府立医科大学の夜久均学長、八木田和弘副学長、曽和義広特任教授に、同フォーラムの活動、イベント開催の経緯や参加者の声(前編)、図書館施設の今後の活用(後編)などについて聞きました。
京都府医科大学
学長
夜久 均(やく・ひとし)
1957年 大阪生まれ
1982年 京都府立医科大学卒業
1984年 国立循環器病センター心臓血管外科レジデント
1988年 国立循環器病センター研究所研究員
1990年 Vermont大学(Burlington, USA)研究員
1993年 St. Vincent’s Hospital (Sydney, Australia) 心臓胸部外科
1997年 京都府立医科大学帰学
2004年 京都府立医科大学心臓血管外科学教授
2019年 京都府立医科大学附属病院長
2023年 現職
副学長
八木田 和弘(やぎた・かずひろ)
1969年 徳島県生まれ、香川県育ち
1995年 京都府立医科大学卒業
1995年 京都府立医科大学第三内科研修医
2000年 神戸大学 医学部 助手(第二解剖学)
2004年 名古屋大学理学部COE生命システム学 助教授
2007年 大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学 准教授
2010年 京都府立医科大学 統合生理学 教授
2023年 京都府立医科大学 副学長(兼務)現在に至る
特任教授
曽和 義広(そわ よしひろ)
1964年 大阪生まれ
1988年 京都府立大学 農学部卒業
1990年 京都府立大学大学院 農学研究科(修士課程)修了
1996年 京都府立医科大学大学院 医学研究科(博士課程)修了
1999年 京都府立医科大学 学内講師(公衆衛生学)
2000年 京都府立医科大学 講師(公衆衛生学)
2002年 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 客員研究員
2004年 文部科学省 科学技術政策研究所 客員研究官
2008年 京都府立医科大学 准教授(予防医学)
2022年 京都府立医科大学 教育センター 特任教授 現在に至る
―ラーニングコモンズ「Koto Square」の役割とは?
夜久学長:学生たちがアクティブラーニング、集いや憩いの場として活用するのはもちろん、学生や教職員だけでなく、他大学や企業、他の国の人々も交流できるような空間にしたいと思っています。本学は公立単科大学のため、特殊で閉鎖的な組織であり、新しいものは生まれにくい環境。広い世界観を養い、違う経験や考え方をもつ人たちとの交流を意識しないと大学としても成長しにくいのです。そういう意味でも、この場所を様々な催しで使っていきたいと考えています。そして、学生、研究者、医師だけでなく、職種に関係なく府民の方々にもぜひ利用いただきたい。まだ計画中ですが、図書館内にカフェを設置する予定です。府民の皆様にも気軽にカフェを利用いただき、学生と話したりしてもらえると、学生たちにとっての学びにも繋がるでしょう。

曽和特任教授:場所や機会が人を創るということもあります。いろんな人と出会うことはすごく大事ですよね。特に全然知らない人と接することでインスパイアされたり、自分自身が人に与えるものに気づいたり。例えば、医療の問題が医学だけで解決できないこともあります。理工系の人、場合によっては人文系の人と交流し、知識やアイデアを交わすことで解決のヒントになることもあるでしょう。そういう出会いの場所になるといいですね。
―ラーニングコモンズ活用のアイデアは?
夜久学長:医科大学の図書館の中で、斬新な芸術や京都ならではの伝統文化などを通して新しい出会いを創出できれば面白いですね。
八木田副学長:畳のスペースもありますし、お茶会をするのもいいですね。池谷附属図書館長も顧問をされていますし。表・裏それぞれ茶道部に協力してもらって、海外の留学生を招いておもてなしするとか。いけばなを習っている学生も多いですから、華道の展示などもできそうです。あとは狂言、2階ホールで公演を鑑賞後、ラーニングコモンズでワークショップを開催するなど。本当にあらゆる使い方が可能ですし、これから活用していく中で、どんどん新しいアイデアも出てくるのではないでしょうか。

曽和特任教授:府立医大には病気になってから来るのではなく、学生だけでなく府民の方にも、普段から「何かやってる」「面白そう」「入ってみよう」くらいの近しさや親しみを持って、来てもらえる、開かれた場所になるのが理想的です。ファミレスのような広いテーブル席、木の柱に囲まれたハイカウンター席、畳のスペース、ビーズクッションがあって寝転べるスペースなど、いろんな雰囲気の空間があり、使い方次第、使う人の発想で、自由度高く使っていただけると思います。

夜久学長:こういう素晴らしい空間ができましたので、使う頻度をどんどん増やして、閑散とした時間がないように、常に何かをやっているような活気ある図書館をめざします。
―学内の学生たちに期待する使い方は?
夜久学長:他大学の学生や仲間を呼んで来て、語り合ったり、勉強会やイベントなどを開催したりしてくれるといいですね。本学の学生だけじゃなくて、医学とは違う分野の人も含めて、学生たちがここに座って交流することを望みます。特に京都は人口に占める大学生の割合が日本一の「大学のまち」として知られています。交流のチャンスはたくさんあるはずですから、ぜひお互いの視野を広げる場に使ってもらいたいですし、学生たちからの新しいアイデアが出てくることも期待しています。 八木田副学長:世界各地の壁や道路に作品を残しているイギリスを拠点とするアーティストのバンクシーの名言に「予め許可を取るよりも、後で謝って許してもらうことの方が、常に簡単である」という意味の言葉があり、私もよく講義で言っています。そんな感じで学生たちに「こんな使い方するのか?」みたいなことにもチャレンジして欲しい。トリアス祭に開放して、ユニークな使い方をした人を表彰するアイデアコンテストなども面白いかもしれません。
―ラーニングコモンズ整備等へのクラウドファンディングや寄付にご支援くださった方々へのメッセージを。
夜久学長:予想を遥かに超えるご支援をいただき、心より感謝申し上げます。非常に多くの方々が関心をもってくださり、それだけの期待が込められていることを真摯に受け止めております。「学生時代に附属図書館にはお世話になりました」「患者として府立医大を応援しています」「ラーニングコモンズを通して、未来の医療人育成を」といったメッセージも多数いただきました。ご支援くださった皆様の期待にお応えできるよう、多くの方々へ開かれた場所としてご活用いただけるよう、責任をもって運用していかなければならないと改めて背筋を伸ばしております。