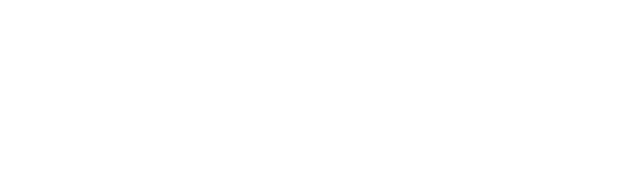#8 図書館ホール+ラーニングコモンズ活用事例 京都クオリアフォーラム「第7回お互いを知ろうの会」〈前編〉
“雰囲気も機能も異なる2つの空間で 新たな気づきや意識が生まれる”

令和7年4月、京都府立医科大学附属図書館内にラーニングコモンズ「Koto Square」が完成しました。4月8日にテープカットと内覧会を行い、翌9日はこけら落としとして、京都クオリアフォーラムの「第7回お互いを知ろうの会」を開催。2階の図書館ホールとの併用で活動報告、部会ミーティング、デモ展示など、産学、異業種の方々約100名の参加がありました。京都クオリアフォーラムの運営にも携わる京都府立医科大学の夜久均学長、八木田和弘副学長、曽和義広特任教授に、同フォーラムの活動、イベント開催の経緯や参加者の声(前編)、図書館施設の今後の活用(後編)などについて聞きました。
京都府医科大学
学長
夜久 均(やく・ひとし)
1957年 大阪生まれ
1982年 京都府立医科大学卒業
1984年 国立循環器病センター心臓血管外科レジデント
1988年 国立循環器病センター研究所研究員
1990年 Vermont大学(Burlington, USA)研究員
1993年 St. Vincent’s Hospital (Sydney, Australia) 心臓胸部外科
1997年 京都府立医科大学帰学
2004年 京都府立医科大学心臓血管外科学教授
2019年 京都府立医科大学附属病院長
2023年 現職
副学長
八木田 和弘(やぎた・かずひろ)
1969年 徳島県生まれ、香川県育ち
1995年 京都府立医科大学卒業
1995年 京都府立医科大学第三内科研修医
2000年 神戸大学 医学部 助手(第二解剖学)
2004年 名古屋大学理学部COE生命システム学 助教授
2007年 大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学 准教授
2010年 京都府立医科大学 統合生理学 教授
2023年 京都府立医科大学 副学長(兼務)現在に至る
特任教授
曽和 義広(そわ よしひろ)
1964年 大阪生まれ
1988年 京都府立大学 農学部卒業
1990年 京都府立大学大学院 農学研究科(修士課程)修了
1996年 京都府立医科大学大学院 医学研究科(博士課程)修了
1999年 京都府立医科大学 学内講師(公衆衛生学)
2000年 京都府立医科大学 講師(公衆衛生学)
2002年 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 客員研究員
2004年 文部科学省 科学技術政策研究所 客員研究官
2008年 京都府立医科大学 准教授(予防医学)
2022年 京都府立医科大学 教育センター 特任教授 現在に至る
―「京都クオリアフォーラム」とは? ホームページはこちらから。
夜久学長:京都に根ざす大学と企業が互いの垣根を越えた交流を通して“「知」の共鳴場”を実現すること、そこから新たなイノベーションを創出し、社会実装を通して日本の科学技術、産業界に貢献して、世界をリードする人材を輩出することを目的として設立されました。「共同研究、事業開発」では、①スマート農業、②健康・医療・介護、③エネルギー・モビリティの3つの部会で地域の問題解決に取り組んでいます。そして、これらのテーマ探索や協働を通して、人材を育成する活動を推進しています。現在は京都と奈良の9大学、京都の8企業が参加しており、私は代表者会議のメンバー、八木田副学長は幹事、曽和特任教授は①と③の部会の本学担当者を務めております。
曽和特任教授:本学としては、やはり健康・医療・介護が専門であることからメインの課題ではありますが、医療に携わっていると、食の問題についての要望が結構あります。そこで、健康やウェルビーイングなどにも関連するスマート農業に軸足を置いています。一方、エネルギー・モビリティも、特にモビリティに関しては、人や物の移動について、今後、地域の医療課題として出てくるはずです。課題解決に向けて企業とアカデミアで知恵を出し合い検討を進めています。本学としても取り組むべき問題として、京都クオリアフォーラムに貴重な機会をいただいています。

―「第7回お互い知ろうの会」開催の経緯は?
八木田副学長:同様のコンソーシアムは他地域にもありますが、我々は京都ならではの付き合い方で、お互いの信頼関係を大切にしようと。堀場厚会長(株式会社堀場製作所 代表取締役会長兼グループCEO)の言葉で言うと「“不細工”なことはしない」を不文律としています。信頼関係の醸成のため、まずは産学、異業種がお互いを理解する「お互いを知ろうの会」を年2回継続しています。これまで持ち回りで開催してきましたが、本学は100人以上の参加者を収容できる場所を提供することができなかったのです。「そろそろお願いできませんか」という連絡をいただいた時に、ちょうどラーニングコモンズが完成する時期であることがわかり実現したという経緯です。ベストなタイミングでこけら落としになりました。

―参加者の反応、感想などは?
八木田副学長:非常に好評でした。その理由として、まずはホールとラーニングコモンズが館内に併設されていることで、移動がすごく楽だと。ホールの設備も充実しており、ホールとラーニングコモンズをセットで使える、このレベルの施設はなかなかないと喜んでいただきました。さらにラーニングコモンズは自由にアレンジできるので、機能的で使いやすいという感想もいただいています。3つの部会がエリアを分けて、同時進行でプレゼンをするのは初の試みでしたが、お互いを邪魔せず、自由に回遊しながら聞いていただくことができました。ポスターやデモ展示例などもあり、興味ある人が集まっていくという形で、さながらミニ万博のようでした。京都府立医科大学でこういうスタイルの催しができるというのは、新たな発見だったようで、もっと色々なイベントで使わせてほしいとのお声もいただいています。
夜久学長:2階のホールでは、落ち着いた雰囲気で着席して講演や講義を集中して聴き、階段を降りると明るい空間の中で、自由にディスカッションできる。2つのモードを同じメンバーで時間を変えてできることで、新たな気づきや意識が生まれ、議論も進むという効果もあるのかもしれませんね。

―京都クオリアフォーラムの今後の活動予定は?
曽和特任教授:7月にまたこちらで、京都クオリアフォーラムの各大学の博士課程の学生と、企業や大学の博士号取得者を繋ぐイベントを開催します。京都クオリアフォーラムのもう一つの柱である「人材育成」についても、企業や大学の枠を超えて、みんなで応援していこうという取り組みです。このラーニングコモンズの鮮やかで色とりどりの椅子、机、カーペットは、いろんな大学、企業、独自の色を持っている人たちが集まる空間として最適だと思うのです。サラダみたいに豊かな彩りで、いくつもの味わいを楽しめる。本学のような公立単科大学ではどうしても一つの色になりがちで、同じような人達が集まってもブレークスルーはなかなか起きにくいのですが、多様な属性の人が集まって、わいわい、がやがやと過ごすことで、固定概念を打ち破っていける場所になるのではないかと期待しています。