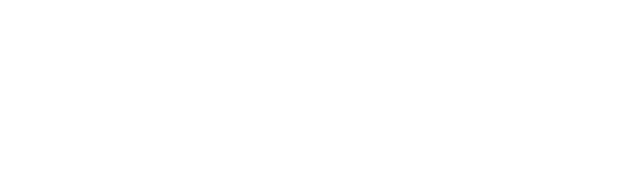#18 総合地球環境学研究所 所長 山極 壽一さん〈後編〉
“本との対話、人との対話が 生きる力を育む”

ゴリラ研究の第一人者であり、霊長類の進化の過程から「人間とは何か」を探究してきた人類学者/霊長類学者の山極壽一さん。2020年まで京都大学総長を務めておられた際、産学連携プロジェクト「京都クオリアフォーラム」発足において、京都府立医科大学と協働したことを契機に、本学150周年記念講演にもご登壇いただきました。現在は、総合地球環境学研究所所長である山極さんに図書館の思い出や読書の魅力(前編)、地球環境学の研究活動、大学教育への思い(後編)などをお話しいただきました。
総合地球環境学研究所 所長 山極 壽一(やまぎわ・じゅいち)
1952年(昭和27年)、東京都生まれ。人類学者/霊長類学者、ゴリラ研究の第一人者。京都大学理学部卒、同大学院で博士号取得。京都大学霊長類研究所などを経て同大学教授、2020年(令和2年)まで第26代京都大学総長。2021年(令和3年)より総合地球環境学研究所所長。2025年(令和7年)国際博覧会<大阪・関西万博>シニアアドバイザーを務める。著書に『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』(家の光協会)、『京大というジャングルでゴリラ学者が考えたこと』(朝日新書)、『共感革命-社交する人類の進化と未来』(河出新書)など多数。
ー総合地球環境学研究所(以下、地球研)とは?
総合地球環境学は英語で「Research Institute for Humanity and Nature」、自然科学の研究と思われるかもしれませんが、人文学の研究機関のひとつです。初代所長の日高敏隆先生が「地球環境問題の根幹は言葉の広い意味での人間の文化の問題である」と言って始まった文理融合の研究をしています。私が子どもの頃、1950~60年代は、団地が次々に建てられ、舗装道路ができ、工場も増え、中央高速や新幹線が開通するなど、どんどん変わる街の風景が、日本の発展の象徴だと、それが当時の文化の価値観でした。しかし1970年代になると、光化学スモッグや水俣病、四日市ぜんそくなど公害の影響が出始め、こんなことを続けていたら人間が滅んでしまうと考え直し、価値観が変わりました。価値観が変わることで環境も変わり、環境が変わることで価値観も変わる、つまり相互に影響し合うというのが私の考えです。環境というと気候温暖化や海水温上昇などグローバルな問題が注目されがちですが、身近な足元から見ていくとまさに価値観の問題。文系・理系の研究者たちが人間の社会や文化とともに地球環境問題の研究に取り組んでいます。

ー所長としての職務は?
環境問題は、学者や研究者だけでは解決には至りません。地域の自治体やNGO、そこに暮らす方々と話し合い、知恵を借りて、具体的な解決策を作り、実装できる超学際研究を目指しています。ごみ問題、ブッシュミートと呼ばれる野生動物の食肉の問題など、文化と環境に関わる問題の研究プロジェクトを募集し、地球研が資金を出して文理融合での研究をサポートしています。1つのプロジェクトに80~150人ほどの分担者や協力者がおり、そのマネジメントが私の仕事です。現在は7つのプロジェクトが進行中で、最大8年にわたるものもあります。私はゴリラの研究をする中で、調査した場所でNGOを作り、地元の人たちと一緒にゴリラを保護する活動を30年以上続けてきました。地元の人たちと意見を交わし合い、ゴリラだけでなく野生動物たちが共存していくための対策を具体的に考え、実践する。昔は自分の研究対象を保護する必要はなかったのですが、人口圧の高まりにより、保護活動をしないと研究対象がいなくなってしまうようになりました。これは私の恩師・伊谷さんの研究とは一つだけ違う点で、私が始めた活動です。地球研ではゴリラの研究はしていませんが、私のこうした経験を生かして超学際研究を推進しています。
ーゴリラ研究の視点から人間教育についての講演などもされていますが、未来を担う医療人たちを育成する医科大学の教育の中で大切にすべきことは?
「生きる力」を学んでほしいと思います。知識はインターネットにもあり、知識を得るために大学で学ぶ必要はないんです。じゃあ一体大学で何を学ぶのかというと実践です。それぞれの頭の中にあるもの、アウトプットできないものを会話によって、あるいは手作業で、実際に手を動かす技術とはどういうものなのか、経験のある人といっしょに実践することが学びになる。それはフィールドワークでもあると思います。医科大学のような医学の現場では、体験した人といっしょに手を動かす、同時に頭を動かすことが必要でしょう。インターネットの中で好きな情報を取り出すだけでは生きる力は生まれません。私が子どもの頃からやってきた本との対話で、過去に生きた人たちの人生や物語を自分の心や体に取り込むこと。環境も社会も、急速に変わりつつある世界では、過去の知恵を土台に自分なりに新しいことを作り上げないと対処できないし、立ち向かっていけません。そして、人との対話。生の言葉は情報と違い、声のトーンやピッチ、相手の個性、状況などが組み合わさって言葉になる。それを受けて、自分の身体の中で、自分の経験とともに解釈して、体系化され拡張されて、自分の言葉や行為に現れたら、それは言葉のもつ大きな影響力でしょう。共感や共鳴によって自分の身体を通して考えることが大切なのです。そのためにはやっぱり出会いと気づきをもたらしてくれる、本との対話、人間との対話を重視してもらいたいと思います。