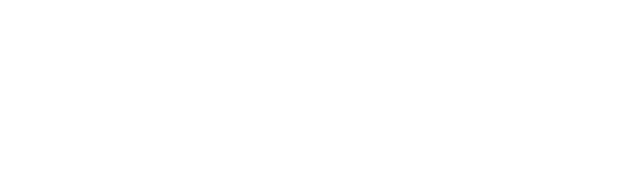#16 小林さやかさん〈後編〉
“挑戦のプロセスで何を学び どう成長したのかに光を当てる”

映画化もされたベストセラー『学年ビリのギャルが一年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』(坪田信貴著)の主人公として、一躍脚光を浴びた「ビリギャル」こと小林さやかさん。現在は、講演や執筆活動を行うほか、アメリカの名門・コロンビア大学教育大学院での学びを経て「日本人のマインドセットを変える!」をミッションとする英語学習事業にも取り組んでおられます。大学受験に向けた学びの原動力となったもの、私を変えた一冊(前編)、図書館の思い出、これからの教育で大切にすべきもの(後編)などをお話しいただきました。
小林さやか(こばやし・さやか)
1988年(昭和63年)、名古屋市生まれ。中学・高校でビリを経験。素行不良で何度も停学になり、高校2年生のときの学力は小学4年生のレベルで偏差値は30弱だったが、塾講師の坪田信貴氏との出会いを機に大学受験を目指す。その結果、1年半で偏差値を40上げて慶應義塾大学に現役合格を果たした。その経緯を描いた坪田氏の著書『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』は120万部を超えるミリオンセラーとなり、映画化もされた。大学卒業後はウェディングプランナーの仕事に従事した後、「ビリギャル」本人として講演や執筆活動を行う。21年、聖心女子大学大学院文学研究科人間科学専攻教育研究領域博士前期課程修了。24年米国コロンビア大学教育大学院修了。近著に『私はこうして勉強にハマった』(サンクチュアリ出版)がある。25年、「日本人のマインドセットを変える!」をミッションに英語学習事業を開始予定。
ー図書館にまつわる思い出は?
2022年~24年秋までニューヨークへ留学していたのですが、ニューヨークではずっと図書館にいました。コロンビア教育大学院での授業は宿題が本当に多くて、ウィークデーは大学院の図書館、休みの日は空気を変えて、ニューヨーク市立図書館で勉強しました。図書館では自分のことに集中して本を読んだり、勉強したりしている人が多いじゃないですか。あれはラーニングピア効果、ピアプレッシャーとも言って、周りにがんばって取り組んでいる人がいると自分もがんばろうとモチベーションが高まります。一人で勉強するよりも、周りからのプレッシャーでやる気が出るという効果があるので、図書館に行って自分に負荷をかけていました。大学受験の時も、私のクラスはエスカレーター式進学コースで、受験勉強する人はいなかったんです。そんな中、一人で勉強するのはきつかったので、図書館に行って、ものすごい殺気立って勉強している人を見つけて、その近くに座って、一緒に勉強しているような、勉強しなきゃという気持ちになれる環境を作っていました。アメリカの図書館は、レトロで重厚で、天井が高くてハリー・ポッターの世界のようでした。日本の図書館は施設が綺麗だし、「今月のおすすめ本」みたいな紹介もあって、ホスピタリティを持って運営しておられるなと感じます。
ー「日本人のマインドセットを変える!」をミッションに英語学習事業を開始されるとのこと、どのような内容ですか?
日本の教育を変えたいという思いがあり、外から日本を見ることも必要だと、34歳で初めての海外生活を経験しました。日本は教員も真面目で熱心ですし、読み書きできない子どもがいないというのは、世界的に見ても質の高い教育だと思います。でも「失敗させない」ことを重視しているのは残念なこと。失敗してこそ、試行錯誤して学べるんです。1回も失敗せずに成功するなんて無理、失敗からの成功体験を積み上げることで、自信や自己効力感が芽生えます。認知科学的にも、この失敗させない、リスクを取らせないマインドセットを変えないと、今、世界中から評価されている日本の良さに日本人が気づかない、それがもどかしくて。マインドセットを変えるビジネスを考えた時に、使えると思ったのが英語でした。私は英語が十分に話せない状態で留学しました。私も日本人だから「間違えたくない」「変なことを言って笑われたくない」と思って授業で発言することもできませんでした。しかし留学して1年ほどたった時に、せっかくアメリカに留学したんだし、友だちも作りたいし、授業でもいっぱい発言したい、間違えたっていいやと割り切ったら、そこから英語力が大きく伸びました。私が実際に英語を話せるようになったメソッドで、英語をツールとしてマインドセットを変えていくという英語学習事業に取り組んでいます。

ーこれからの日本の教育で大切にすべきことは?
失敗させること、まずは大人が賢くリスクを取ることが大切だと思います。例えば、受験もどこを見るかによって、リスクが変わってきます。結果だけを見て、結果を点として捉えてしまうと不合格になることがリスクになる。不合格になることがリスクだったら、もし落ちてしまったらすべて終わりという気持ちになる、そんなの怖くて挑戦できません。当日に体調を崩して実力が発揮できないこともあるし、どれだけがんばっても望んだ結果が出せないこともあります。それよりも、そのプロセスで何を学び、どう成長したのかということに光を当てた瞬間に「挑戦できたこと自体がよかったよね」という言葉になりますよね。Process-Oriented Feedback(プロセスに光を当てて、フィードバックする)が人を伸ばすコツ、Outcome-Oriented Feedback(結果や成果に光を当てて、フィードバックする)だと、もう二度と挑戦できないマインドセットが育ってしまう、というのを論文でもたくさん読みました。受験で合格したら成功、不合格だったら失敗、こんな短期的なことでいいんでしょうか。人生をもっと長期的に見て、積極的にいろんなことに挑戦できるマインドセットを持っている方が、絶対に幸せになれるはず。周りの大人が注力しすぎて、子どもが自信をなくしてしまっている状況をよく見ます。大人がプロセスに光を当てて、挑戦することや失敗してもそこから学んで、また挑戦できることを評価できる環境があれば、子どもたちはどんどん伸びると思います。ビリギャルを生んだのは、母の失敗を恐れない子育てと、坪田先生のアプローチ、そういう環境に恵まれたから。私はとてもラッキーだったと思っています。