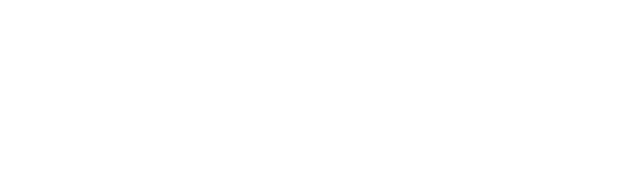#15 小林さやかさん〈前編〉
“解きたい問い、知りたい謎を得て 私は「学び」に目覚めた”

映画化もされたベストセラー『学年ビリのギャルが一年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』(坪田信貴著)の主人公として、一躍脚光を浴びた「ビリギャル」こと小林さやかさん。現在は、講演や執筆活動を行うほか、アメリカの名門・コロンビア大学教育大学院での学びを経て「日本人のマインドセットを変える!」をミッションとする英語学習事業にも取り組んでおられます。大学受験に向けた学びの原動力となったもの、私を変えた一冊(前編)、図書館の思い出、これからの教育で大切にすべきもの(後編)などをお話しいただきました。
小林さやか(こばやし・さやか)
1988年(昭和63年)、名古屋市生まれ。中学・高校でビリを経験。素行不良で何度も停学になり、高校2年生のときの学力は小学4年生のレベルで偏差値は30弱だったが、塾講師の坪田信貴氏との出会いを機に大学受験を目指す。その結果、1年半で偏差値を40上げて慶應義塾大学に現役合格を果たした。その経緯を描いた坪田氏の著書『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』は120万部を超えるミリオンセラーとなり、映画化もされた。大学卒業後はウェディングプランナーの仕事に従事した後、「ビリギャル」本人として講演や執筆活動を行う。21年、聖心女子大学大学院文学研究科人間科学専攻教育研究領域博士前期課程修了。24年米国コロンビア大学教育大学院修了。近著に『私はこうして勉強にハマった』(サンクチュアリ出版)がある。25年、「日本人のマインドセットを変える!」をミッションに英語学習事業を開始予定。
ー高校2年生で小学4年生の学力レベル、そこから1年半で慶應義塾大学に現役合格を果たされましたが、その原動力となったものは?
「ビリギャル」の著者でもある、塾講師の坪田信貴先生への憧れですね。坪田先生は、私にとって出会ったことのない大人でした。高校生の頃は、父と仲が悪く、私の外見だけで判断して「もうダメだ」というレッテルを貼られていました。学校の先生たちは「お前は人間のクズで、学校の恥だ」と。周りの大人たちは私の良さを理解しようとしてくれなかったんです。坪田先生は、私の話を真摯に聞き、私のいいところを嬉しそうに伝え、やる気を引き出してくださって。やっと私の理解者が現れたみたいな気持ちになって、すごく嬉しかったです。先生のように、博識で、幅広い視野で、冷静な判断ができる、私もそんな人になりたいと思うようになりました。そのためには、勉強することが近道になるかもしれないと。そして名古屋から出て、もっと広い世界にアクセスしたいと考えたのも、坪田先生への憧れだったと思います。坪田先生は、結果だけではなく「ここまでよく来たよね」とプロセスも評価して、どんな時も私のことを信頼してくださっていたことも原動力となっていました。今でもお兄ちゃんみたいに、いろんな話をしたり、相談したりできる相手です。ちなみに、父とも今は仲良くしています。映画のラストで、東京へ旅立つ前に、子どもの頃を思い出して、父におんぶしてもらうシーンがあります。父親世代の方からは「あのシーンで泣いた」というご感想をよくいただきます。
ー大学受験に挑戦されたことで、気持ちや行動に変化はありましたか?
大学卒業後、ウェディングプランナーの仕事をしている時に、坪田先生が著書を出版され、ビリギャル本人である私に講演依頼が来るようになりました。いろんな教育活動に従事させていただく中で「なぜ私にあんなことができたんだろう」という問いが生まれてきました。「地頭が良かったから」とよく言われるのですが、慶応に合格するまでは、地頭が悪いと言われていたんです。「地頭って何?」「地頭以外の理由があるはず」と、聖心女子大学大学院で学習科学の分野で、子どもたちのパフォーマンスが最大化するアプローチや学習環境を学びました。さらにコロンビア大学教育大学院で、認知科学を学びました。私が特に興味があったのは、自分に対する評価、自分はできると思うことがパフォーマンスにどのように影響するかということでした。私の母は大阪生まれで、関西人の「やってみなはれ」の精神、失敗を恐れない子育てをしてくれました。それが私に必要なマインドセットを培ったのではという仮説があり、認知科学を学んでみると、やはり母の子育てが効果的であったことがわかりました。私は「勉強」ではなく「学び」に目覚めたのだと実感しています。解きたい問い、知りたい謎が得られると、人は前のめりになって学びます。勉強は受動的ですが、解きたい問いがあると能動的になれるんです。

ー〝私を変えた一冊〟は?
高校2年の夏から1年間、毎月1冊、坪田先生が選んだ本を読んで感想文を書くという課題がありました。私はそれまで本を読んだことがなかったんです。「それじゃあ小論文書けないだろう」ということで、まずは本を読んで感じたことを文章に書くことから始めました。1冊目は山田詠美さんの『ぼくは勉強ができない』という小説、『ハリー・ポッター』や日本の近代文学『蜘蛛の糸』『雪国』など、幅広いジャンルを読みました。その中で読んだ『14歳からの哲学』が特に印象に残っています。慶応大学文学部卒の池田晶子さんの書かれた14歳でも読める哲学書。生きるとはなにか、考えるとはどういうことかなど、いわゆる答えのないことが、わかりやすく柔らかい言葉で綴られています。それまで哲学に触れたことはなかったし、何かを考えるって面倒なことだと思っていました。生きるとはなにか、命とは、といったトピックに対して、読者自身が考えられる、トリガーになるような言葉が書かれていて、本来私たちが考えなければいけないこと、答えのないことを考えてみるのは面白いと思える、初めての感覚でした。坪田先生は、哲学と心理学を学び、人の気持ちに寄り添ったり、モチベーションを引き出したりすることに長けておられて、どうしたらこんな人になれるんだろうと思っていました。この本を読んで、少しだけ坪田先生の考え方が理解できたような気がしました。