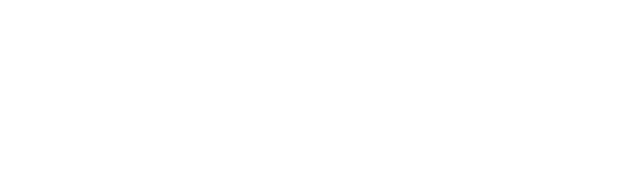#17 総合地球環境学研究所 所長 山極 壽一さん〈前編〉
“物語を読んでイメージできるのは 人間だけの特殊な才能”

ゴリラ研究の第一人者であり、霊長類の進化の過程から「人間とは何か」を探究してきた人類学者/霊長類学者の山極壽一さん。2020年まで京都大学総長を務めておられた際、産学連携プロジェクト「京都クオリアフォーラム」発足において、京都府立医科大学と協働したことを契機に、本学150周年記念講演にもご登壇いただきました。現在は、総合地球環境学研究所所長である山極さんに図書館の思い出や読書の魅力(前編)、地球環境学の研究活動、大学教育への思い(後編)などをお話しいただきました。
総合地球環境学研究所 所長 山極 壽一(やまぎわ・じゅいち)
1952年(昭和27年)、東京都生まれ。人類学者/霊長類学者、ゴリラ研究の第一人者。京都大学理学部卒、同大学院で博士号取得。京都大学霊長類研究所などを経て同大学教授、2020年(令和2年)まで第26代京都大学総長。2021年(令和3年)より総合地球環境学研究所所長。2025年(令和7年)国際博覧会<大阪・関西万博>シニアアドバイザーを務める。著書に『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』(家の光協会)、『京大というジャングルでゴリラ学者が考えたこと』(朝日新書)、『共感革命-社交する人類の進化と未来』(河出新書)など多数。
ー図書館の思い出は?
昔から本が好きで、小・中・高校と図書館に入り浸っていました。大学から京都へ来てよかったなと思ったのは古本屋が多い街だったこと。今はずいぶんとなくなってしまいましたが。私が子どもの頃や学生の頃は、新しい知識は「本」と「人」から得ていたんです。だから、新しい知識を先生や仲間から教えてもらって、図書館に行って本を読む、そのために学校に行っていました。本というのは、過去からのメッセージですよね。そして物語を教えてくれるんです。
ー子どもの頃に好きだった本は?
伝記本が大好きでよく読みました。その人の残した輝かしい業績だけでなく、どういう人生を送ったのか、どうやって死んだのかまで、一生のことが書いてある。人生には浮き沈みがあり、いろんな出会いがあり、世界を驚かせるような業績は本人の能力や経験に加えて、偶然の巡り合わせや運もあるんだと、人生は面白いなと思いました。探検も好きで、当時の日本ではなかなか探検できることはなかったので、本で読む海外の未発見の場所に憧れていました。知らない世界が本の中にあり、未知のものを探検する場所でもありました。伝記本でも、未開のアフリカの僻地に赴き医学で人々を救ったシュバイツァー、探検家であり医師でもあるリビングストンなど、探検のストーリーがあるものが特に好きでした。青年期になると『若きウェルテルの悩み』なんかを読んで、時代ごとに同じようなことを考えていた人がいたんだと共感し、心に抱える悩みや夢などの結末や見解を得ました。勇気や生きる力を与えてくれる本をむさぼるように読んでいました。

ー私を変えた一冊とそのエピソードを聞かせてください。
私の恩師・伊谷純一郎が1963年(昭和38年)に書いた『ゴリラとピグミーの森』(岩波新書)は、本当に私の人生を変えた、私のバイブルとも言える一冊です。1960年に伊谷さんが単身で、アフリカの奥地の森林にゴリラの調査へいった時の旅日記で、最初のシーンがすごくいい。伊谷さんがケニアのバーでケニア人に1杯ご馳走するんです。バーテンダーのインド人は「こんな奴におごる必要ない」と言いますが、1960年はアフリカ独立の年、ケニアも独立の喜びに溢れていて、その雰囲気を祝福したいという伊谷さんの気持ちの表れだったわけです。伊谷さんはゴリラの調査が目的だったけれど、いっしょに調査してくれたバトワというピグミーの狩猟採集民の人たちと仲良くなり、その人たちの暮らしにも興味をそそられ、対等に付き合うようになります。目で見て、耳で聞くことのすべてが新鮮に綴られていて、フィールドワークの熱気に触れるようでした。これを読んだことがきっかけで「まさに私のやりかったことだ」と思い、すぐさまニホンザルの調査に入りました。人間以外の猿や類人猿の研究に興味があったことと子どもの頃からの探検熱が結びついて、いずれは伊谷さんのようにアフリカへ行くぞ、ゴリラを研究するぞという気持ちになりました。その情熱が今までずっと続いています。
ー読書の重要性、魅力とは?
人間は物語を持たないといけない、事実だけでは生きられない。事実を組み合わせて、想像も含めて一つの物語にしないとしっかりとイメージできないんです。本はその物語を伝えてくれます。一つのまとまった始まりと終わりがあるような物語が、頭にいくつも入ってるっていうことが生きる知恵や力になるんです。物語というパラレルワールド(同時に存在している世界)の中で、主人公の経験が自分の身となり知恵となる。自分と主人公、現実と想像を行き来することで自分の人生に厚みができます。そのパラレルワールドをたくさん持っていることは、自分がいろんな主人公になれるということ。主人公はああやって乗り切れた、だから今自分が立ち向かっている現実はこうすればいいのでは、あるいは本とは違う展開が生まれるかもしれない、そんな風に自分の潜在能力が呼び覚まされる気がします。経験値の少ない若い時にはそれがすごく役に立ったし、自信にもなりました。自分が経験していないことを本や人が語ってくれた物語からイメージできるのは、人間だけの特殊な才能、他の動物にはできないことです。